「せいろって、面倒で難しそう……」
と思っていたのに、気づけば毎週のように使っている。
そんな私が感じたのは、「ちょっとしたアイテムでせいろ生活の快適さが全然違う」ってことでした。
特に“作り置き”をするようになると、
蒸す→冷ます→保存する、という流れを効率化できるアイテムが欠かせません。
「作り置きもしたいけど、時間がない。でもおいしく食べたい」
そんな時にたどり着いたのが“せいろ蒸し”でした。
この記事では、私が実際に使っている便利アイテムを中心に、
「買ってよかったもの」「正直いらなかったもの」までリアルに紹介します。

せいろ歴2年の私が紹介させていただきます!
せいろ生活が充実すると、毎日の食事・暮らしが快適になりますよ◎
せいろ作り置きが続く人の共通点とは?
せいろを続けて使っている人って、意外と「几帳面な人」じゃない。
むしろ、“完璧にやろうとしない人” なんですよね。
私も最初の頃は、
- 毎回ちゃんと蒸し布を敷いて
- きれいに洗って乾かして
- 収納スペースも整えて
……と、気合いを入れすぎて、疲れて続かなかった。
今は、かなりゆるいです。
せいろにキッチンペーパーを敷いて蒸すだけ。
時間も感覚で適当。
それでも、おいしいからまた作ってる。
せいろ生活が続く人の共通点は、
ってことなんじゃない?って思ってます。
作り置きも同じで、
このゆるさが、結果的に“長く続けられる”につながります。
つまり、せいろ使いや作り置きといった自炊が続く人は、
「がんばらない仕組み」を自然に作っている人。
便利アイテムも、その“仕組み”を支えるためにあるだけ。

完璧を目指すより、「ラクに続く」を目指した方がうまくいくんだよな〜。
せいろを続けてきて、私が一番実感したことです。
レビュー|せいろ作り置きにおすすめの便利グッズ5選
せいろ蒸しは、極論、せいろと鍋さえあればできます。
でも、プラスアルファでちょっとしたものを揃えると
実はグッと使いやすく&片付けがラクになるんですよ。
そんな厳選アイテム4つを紹介します。
① クッキングシート(蒸し布の代わりに大活躍)
せいろって、蒸すものによってはこんな問題が。
自然素材のせいろは、特に「色移り」は洗っても落ちない……
なんてことになりかねません。
そこで役立つのが、クッキングシートです。

食材を置く前に、せいろにサッと敷くだけ。
せいろの穴に沿ってシートにもいくつか穴を開けておくと、蒸気の通りがよくなります。

普段づかいのせいろ蒸しって、どっさり食材を入れますよね。
側面も汚れがちなので、敷いとくだけでお手入れがグッと楽になります。
ムラなく仕上げたい、穴を開けるのが面倒という場合は、専用のシートを使うのも◎
② 蒸し板(手持ちの鍋で蒸せる)
せいろ蒸しで困るのが、鍋のサイズ問題。
そんなときに使えるのが、蒸し板です。

使い方はカンタン。
鍋とせいろの間に入れるだけ。

鍋とせいろはピタッと、隙間が無くなってしっかり蒸せます。
ぴったり合う鍋があったとしても、ほかの料理で使いたいってことありません?
そこでその場のフォーメーションに応じて、鍋を使い分けられるのが便利ですよ。
③ 掃除用ブラシ(せいろの隙間掃除に)
肉や魚を蒸すと、どうしてもタンパク質が固まって流れ出してしまうんですよね。
それがセイロの隙間に入りやすいんです。
クッキングシートを敷いていれば防ぎやすいのですが、
どうしても入り込んじゃう時があって。
そんなとき、ごそっと汚れを取ってくれるブラシが使えます。

軽く水を含ませて、せいろをゴシゴシ。

わずかな隙間の汚れもかき出します。
このとき、洗剤は使いません。
せいろは杉や竹、ひのきといった自然素材でできているので
洗剤を使うと入り込んでしまいます。
たっぷりの水で洗い流せば、じゅうぶんです。
こちらはブラシ部分が麻でできていて、“しなり”が心地よくて。
プラスチック製のものと違って、当たりが優しい印象です。
④ ミトン・鍋つかみ(ヤケド防止)
熱湯で蒸し上げるセイロは、できあがりはアッツアツ!
出来立ては素手じゃ持てないので、ミトンや鍋つかみ必須です。

まあ、、、ミトンとは言わず、布巾でもOKです。笑
わたしは、ミトン×布巾の組み合わせで使ってます。

ただし、コンパクトなミトンは持ち上げた瞬間が注意!
蒸気が漏れて、とろとろしてると火傷します。
こういうロング丈タイプは安心。洗えるのもいいし、人気がありますね。
⑤ ミニトング(肉の取り分けに◎)
肉類を蒸す時、「肉類がひっついて、掴みにくい……!」ってことありませんか?
菜箸でも、手に力入っちゃったりして
やりづらいんですよね〜。
そんなとき使えるのが、このトングです。


指先のような感覚でつかめるから、作り置きにも便利なんですよ。
肉に限らず、ちょっとしたものを持てる。

食卓で「ごはんのお供をつまむ」がコンセプトの商品なんですけど、
我が家ではキッチンの下ごしらえで活躍してます。
失敗談|せいろで使ってみてやめたアイテム3選
ほかにも、一般的に良しとされるものはたくさん。
ただ、使ってみたもののイマイチしっくりこなかったものもありました。
蒸し布(メンテナンス性が悪くて断念)
1つ目は、蒸し布です。
どうしても汚れるから、洗ったり乾かしたりケアが必要です。
野菜だと色移りするものがあるし、肉・野菜だと脂っぽくもなるし。

クッキングシートで十分じゃない……?
と気付いてから、蒸し布は選ばなくなりました。
脂っぽくない、色移りのない点心しか蒸さない!
って人はいいのかも。

セイロ用フック(本体が傷みやすい)
2つ目は、セイロ用のフックです。
大きくてかさばるセイロは、吊り下げておくなんて
収納術をよく見かけます。

実際、私もやってました。
でも、これってセイロ本体を傷めてしまうんですよね。
サイズが大きいほど重量が出て、フックだと先端に力がかかってしまうから。
小ぶりな15cmサイズを使っていたときは、吊り下げていたんですが
18cmにサイズアップした途端、フックが食い込んじゃって、、、

それ以来、フックは手放して、置いて重ねる収納に切り替えました。

高さを取るし、しまうと湿気で傷めるのが心配なので
外に出しっぱなしにしてます。
週に何回も使うし、この方が使い勝手もいいです。
キッチンタイマー(スマホ代用でもOK)
最後に、キッチンタイマーです。
蒸す食材によって、放置する時間が変わってくるので
タイマーをかけておくと目安になります。
ただ、蒸しすぎて失敗するってことはないし
私のようなズボラは、慣れてくれば「だいたい5分経ったでしょ」って
感覚だよりで全然OK。
なんなら、スマホでも代用できます。
「濡れた手など、料理中はスマホを触りたくない!」
「時間は厳密に計らなくても、いいや」
こんな人は、必要ないでしょう。
このように、わざわざ買うほどではないけど
っていうアイテムもあるので、手持ちのキッチン用品や環境にあわせて
揃えるのも手です。
+α|せいろ作り置きと相性のいい保存容器・下ごしらえアイテム
ほかにも、セットで使えるものを紹介します。
作り置き用の保存容器
多めに蒸しておいて、取り分けた分を保存しておくのに使えます。
下処理を済ませた野菜は、ジップロックコンテナーが使えます。
かさばる野菜が多いから、カサがあって便利。
スライサー
せいろの上で、すりすりカットするのも便利。
まとめ|せいろ作り置きを“無理なく続ける”コツ
せいろは「続けるほど味が出る」調理道具。
道具に頼るより、“使う人に合ったやり方”を見つけるのが一番のコツです。
この記事で紹介したアイテムが、
あなたのせいろ生活をちょっとラクに、楽しくするヒントになればうれしいです。
「がんばらなくても続けられる暮らし方」が、いちばん長続きするコツ。
今日の夜ごはんに、せいろを出してみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
あなたのお手伝い役「かまい」がお届けしました🤗
「せいろをこれから始めたい」「まずは基本を知りたい」というあなたは
こちらもあわせてどうぞ。
せいろ蒸し生活を送る前は、「作り置きしなきゃ、でも無理……」そんなふうに悩んでいました。
自炊に悩んでいる人の気づきになればと、こちらで語りました。
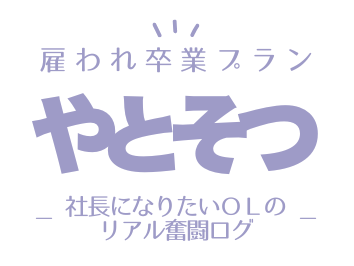








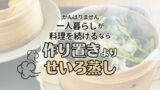

コメント